よくレッスンで、薬膳の効能が書かれた食材辞典のおすすめを教えてほしいと相談を受けます。
結論から言うと、もう好みで選ぶのが良いと思います。
もくじ
薬膳の食材の本の選び方
本屋さんで見比べて、ご自身でピンと来るものを選ばれるのが一番使いやすいです。
見やすさ、字の大きさ、本のサイズ、取り扱っている食材数などしっくりきたものが後々長く使えると思います。
そしてその時に必ずしてみてほしいのが、その時に興味のある食材を調べてみることです。
その食材の探しやすさ(索引、分類があるか)、自分の知りたい情報があるか、情報量など感じてみて、ピンとくるものを選ばれるのがおすすめです。
私が初めて買ったときは“生姜”で見比べてみました。
私が持っている本(初心者向け)
その当時(9年くらい前?)購入したのがこちらです。漢方薬の販売で有名な薬日本堂さんのものです。
当時は持ち歩きたくて、こちらのハンディ版を買いました。ハンディ版は小さい分、掲載される食材の数や情報量が少し少なくなります。なのでサイズがやや大きくなりますが、上のリンクの通常版が使いやすいです。
内容・説明は比較的シンプルで、そのシンプルさと字体・デザインが私は好きでした。
こちらは周りにも持っている方が多かったです。
薬膳だけでなく、西洋医学・栄養学の観点での情報や食べ合わせも載っていて、わりと情報量は多めだと思います。
私は薬膳の観点の説明を主に求めていたので、薬日本堂さんの本の出番が多かったです。
ここは好みの問題だと思います。
学び続けたい方向け
もし薬膳をもっと深めたい、専門用語も出てきてOKであれば、こちらはおススメです。
写真や色は無く、専門用語が使われており、栄養成分も掲載されています。専門用語や栄養成分の用語の解説ページもあります。中国伝統医学の概念なども書かれています。
薬膳スクールで学ばれる方が辞書として使われることも多いです。
食材の効能を身体で楽しむ
他にもいろいろな本が出てきているようですが、先ほども言った通りご自身でピンと来るものを選ばれるのが一番だと思います。
薬膳の観点で食材を見ると、食材選びや食べることがもっと楽しくなります。
「この成分が入っている」というよりも「これはお腹から温めてくれる」というように感覚で効能を表します。
初めは辞典の出番が多いかもしれませんが、覚えると言うより、頻繁に使う食材であれば感覚で染みついてきます。
ぜひ食べて体感で食材の知恵を増やしていきましょう^^








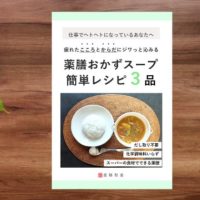
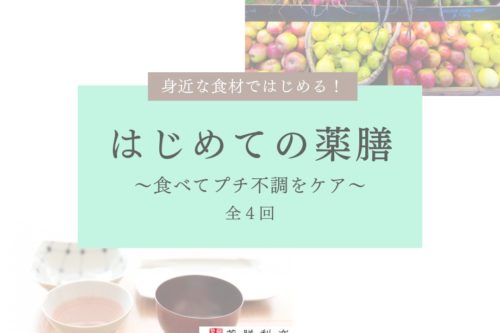

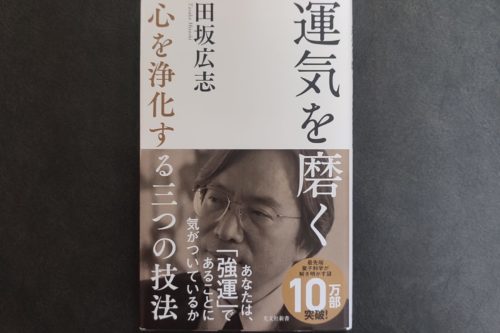






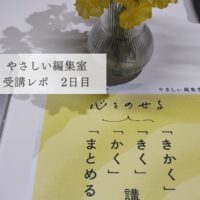
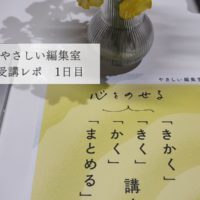


この記事へのコメントはありません。